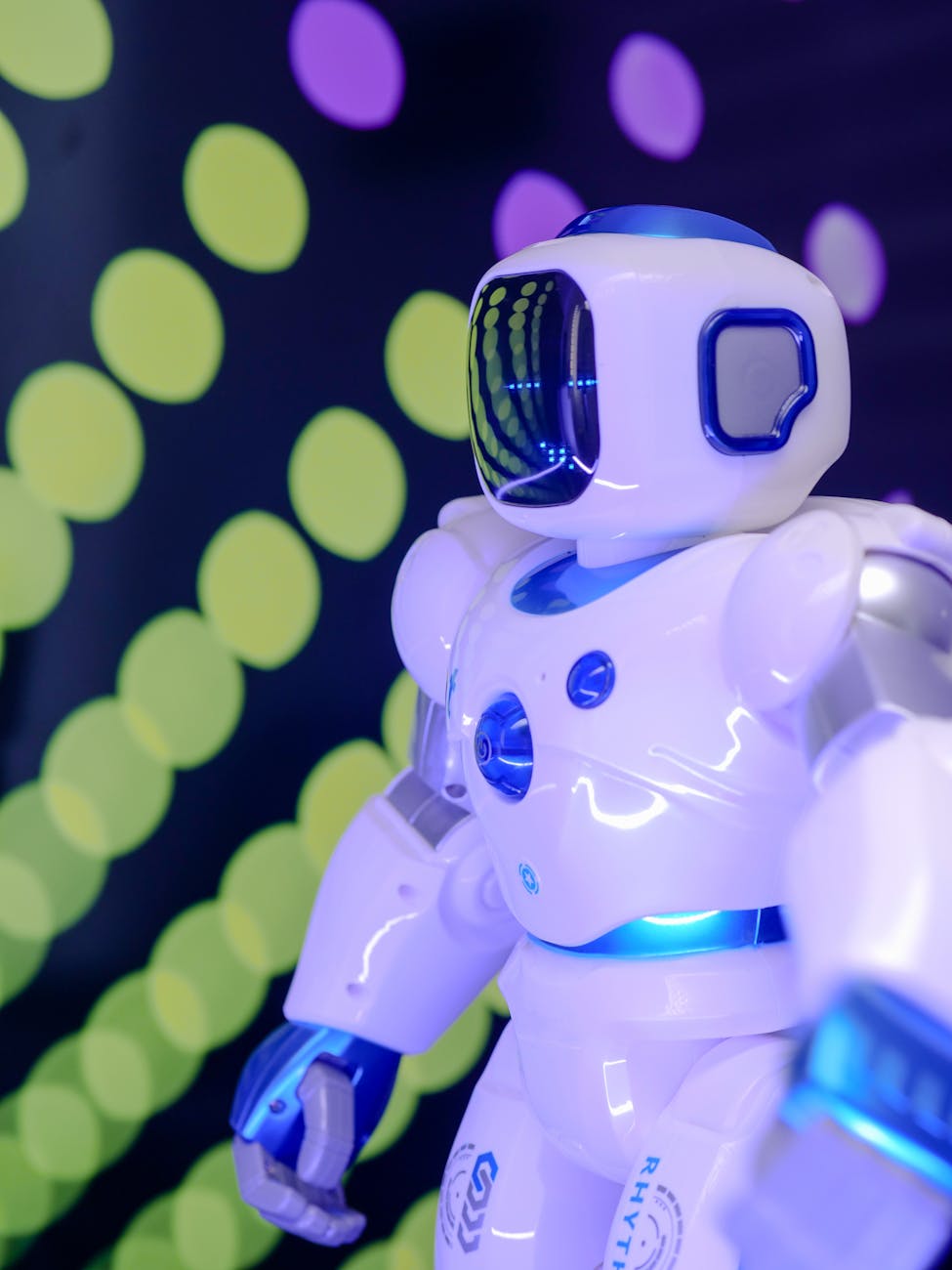【保存版】n8n・Dify・Opal(Google)の徹底比較――ワークフロー自動化/LLMアプリ構築/会話で作れる“ミニAIアプリ”の違いと選び方(2025年版)
先に要点(インバーテッド・ピラミッド)
- n8nは汎用ワークフロー自動化の王道。ドラッグ&ドロップとコードの両立、オンプレ/クラウドの柔軟な運用、「実行回数」課金などでスケールしやすい自動化基盤になります。AIノードも増え、マルチステップのAIエージェントも組めます。
- DifyはオープンソースのLLMアプリ開発基盤。RAG(独自知識の取り込み)・エージェント・ワークフロー・モデル管理/観測性をひとつのUIで扱え、OpenAI/Anthropic/Azure OpenAI/Hugging Face/Replicate等を横断利用できます。商用向けの料金プランも明示されています。
- Opal(Google)は“自然言語で作って共有できるミニAIアプリ”を掲げる新顔。テキストで説明→ワークフロー化という試作特化の無コード体験が売りで、Geminiモデルを活かしたアイデア検証/社内共有に向きます(実験的プロダクト)。
- 用途で選ぶ指針:
- 業務の恒常運用×他SaaS連携×堅牢な再現性→n8n
- ドメイン知識を食べさせた本格LLMアプリ(RAG・エージェント)→Dify
- アイデア実験・社内デモ・軽量な社内Bot配布→Opal(Google)
- 価格と運用:n8nはコミュニティ版の自前ホストが可能、クラウドは実行課金で予算化しやすい。Difyは無料/Pro/Businessのメッセージクレジット制プランを提示。OpalはLabs発の実験提供で、プロトタイピング用途の位置づけです。
1|3製品の「正体」をまず整理:土台・得意分野・思想の違い
n8nは、ZapierやMakeの“開発者寄り”ポジションにあるオープンな自動化プラットフォーム。ノーコードのブロックと任意のコードを組み合わせ、オンプレでもクラウドでも走ります。公式は**「AIワークフロー」「マルチステップAIエージェント」の構築を前面に掲げ、技術チームの基幹オートメーション**まで狙える点が魅力です。
Difyは、オープンソースのLLMアプリ開発基盤(LLMOps)です。RAGのデータセット管理、プロンプトの可視化・反復、エージェント/ワークフロー、モデル横断の切替、ログ/観測性までひとつのUIで扱えます。OpenAI・Anthropic・Azure OpenAI・Hugging Face・Replicateなど複数のモデル・推論基盤をサポートし、**“プロトタイプ→運用”**の橋渡しがしやすい思想です。
Opal(Google)は2025年7月に発表された実験的な無コード“ミニAIアプリ”メーカー。自然言語で要件を書く→そのまま“小さなAIアプリ”に変換し、視覚的なワークフローやテンプレを使ってすばやく共有できるのが特徴。Geminiモデルを活かしたアイデア検証・PoCに最適で、**チームの“AIの取っ掛かり”**として軽快に使えます。
補足:本稿の「Opal」はGoogleのOpalを指します。OPAL(Open Policy Administration Layer)という権限管理OSSも存在しますが、分野が異なるため比較対象外です。
2|「何に強いの?」――ユースケースで比べる三者三様
-
n8n:業務自動化の背骨
- 人事・経理・営業の定型手続き、SaaS同士のデータ連携、Webhook→変換→API書き込みなどの**“配管仕事”を強みとします。AIノードも使えるため、問い合わせ分類→RAG回答→CRM書き込みのような複合自動化**が得意です。
-
Dify:知識を食べるLLMアプリ
- 社内ナレッジ検索(RAG)、FAQボット、要約・要件抽出、ドキュメントQA、簡易エージェントなど、“情報を扱うAI”を運用前提で作るのに向いています。モデル横断・ログと評価・権限ある推論先の切替といった現場運用の悩みを最初からケアします。
-
Opal:会話で作るミニアプリ
- 「まず形に」が必要な場面――新機能の社内デモ、小さなデータ整形/要約タスク、部署内の軽量ワークフロー共有に好適。自然言語→視覚的チェーンへの自動変換で学習コストが極小です。チームへの“AI布教”やPoCの量産がしやすいのが魅力。
3|機能比較:ビルダー体験、統合性、RAG・エージェント、運用
3-1. ビルダー体験(UI/UX)
- n8n:ブロックベースのキャンバス+コード併用。分岐・ループ・エラー処理など作り込む余地が大きく、複雑フローに耐えます。
- Dify:LLM専用の可視化が秀逸。プロンプト/RAG/評価などAI固有の運用部品が最初から揃い、**“AIの本番運用”**に必要なレールが敷かれています。
- Opal:自然言語の説明→ワークフロー化が核心。テンプレや会話的編集で学習ゼロに近い操作が可能。プロトタイプ志向の設計です。
3-2. 接続性・統合
- n8n:SaaSコネクタが豊富で、IT/Ops/Devツールとも相性良好。オンプレ連携も実装しやすく、**“企業の配管”**に向きます。
- Dify:モデルプロバイダの横断に強み。OpenAI/Anthropic/Azure OpenAI/Hugging Face/Replicateほかをサポート。RAGのデータ接続もUIから管理可能。
- Opal:Gemini中心で、Googleアカウントを介した共有やテンプレ活用がしやすい。軽量ワークフローの配布が前提。
3-3. RAG・エージェント
- n8n:外部ベクタDB/LLMと組み合わせて自作。自由度は高いが設計は自分で。
- Dify:RAG・エージェントが“箱”で同梱。評価・観測までUIで回せるのが運用上の強み。
- Opal:簡易チェーンやミニアプリに最適化。本格RAG運用はDify側が得意。
3-4. ログ・観測・権限
- n8n:ワークフロー実行の成功/失敗・再実行が軸。監査性は高いが、LLM特有の評価は自作寄り。
- Dify:プロンプト・RAG・モデル切替に紐づく観測性とロギングをプラットフォーム内で提供。再現性/検証に強い。
- Opal:実験・共有が主眼。運用監査よりも試作スピードを重視。
4|価格・提供形態:予算とスケールの見通しを立てる
- n8n:コミュニティ(自前ホスト)とクラウド。クラウドは**「実行回数」ベースの考え方で、“各ステップ課金”より予算管理しやすいのがポイント。スタートアップ向け割引やエンタープライズ提供**も。
- Dify:無料/Pro/Businessなどのメッセージクレジット制プランを公開。ワークスペース上限/アプリ数/ナレッジ容量/ログ保持など運用の目安が明示されています。学生・教育向け無料の案内もあります。
- Opal:Google Labsの実験的提供としてローンチ。プロトタイピングに最適という公式メッセージで、アイデア検証の加速を主目的に据えています(地域・提供形態は順次変化の可能性)。
5|導入シナリオ別・勝ちパターン(具体サンプル付き)
5-1. n8nで「問い合わせ→AI自動応答→CRM記録」
- トリガー:サポート受信(メール/フォーム)
- 処理:n8nで言語判定→分類→RAG回答生成→翻訳
- 出力:顧客へ返信+CRMに記録+チケット更新
- ポイント:分岐・例外処理・再試行を1フローで完結。“AIありきの業務”を壊さない堅牢さが魅力。
5-2. Difyで「社内ナレッジQAボット(RAG)+評価」
- セットアップ:ナレッジ文書の投入→ベクタ化→RAG設定
- アプリ:QAボットをワークフローで拡張(前処理/後処理)
- 運用:モデル切替や回答ログの可視化、アノテーションで継続改善
- ポイント:RAG/観測性/モデル管理が一枚岩なので、“運用前提のLLMアプリ”を短期間で回せます。
5-3. Opalで「社内デモ:請求書PDFの要点抽出ミニアプリ」
- 作り方:自然言語で**「PDFをアップ→要点抽出→CSVに」**と説明→自動的にチェーン化
- 共有:チームにリンク共有、軽いフィードバックで改良
- ポイント:“まず見えるもの”が数分でできる。Geminiの強みとテンプレでPoCの回転が上がります。
6|セキュリティ/ガバナンスの勘所(現場で起きがちな誤解を解く)
-
データ所在と権限
- n8n:オンプレ運用を選べば機微データも社内完結。監査ログや再実行の仕組みでインシデント追跡が容易です。
- Dify:モデル先の選択(自社契約のOpenAIなど)やナレッジの管理をプラットフォーム内で統制。ログ保持期間やレート制限もプランで管理できます。
- Opal:試作・共有が主眼。社外共有は避ける、匿名化データで検証する等の社内ポリシーを先に決めるのが安心です。
-
モデルの乗り換えと監査性
- Difyは複数モデルの横断と観測性が強く、**“後から証跡を辿れる”**点が実務的。
- n8nは業務ログ中心で再現性に寄与。LLM品質評価は外部の評価指標や専用ログの併設が近道。
7|他ツールとの関係:どこまで代替できる?どこから棲み分け?
-
n8n vs Dify
- 重なる領域:AIノードを使った文章処理や簡易チャットボット
- 差別化:n8n=“SaaS配管×恒常運用”、Dify=“知識×LLMの本番運用”
- 妥協案:n8nで周辺の自動化→DifyのRAG/Agentを呼ぶというハイブリッドが現場最強パターン。
-
Opal vs n8n/Dify
- Opalは作り始めの摩擦が最小。PoC→良かったらn8n/Difyで本格運用という昇格ルートが相性抜群。
8|“選定チェックリスト”(30分で方向性を決めるための12問)
- 自前ホスト必須?(Yes→n8n/Difyいずれも可)
- SaaS配管の比率が高い?(Yes→n8n)
- RAGで社内知識を安全に活用したい?(Yes→Dify)
- モデルを横断で使い分けたい?(Yes→Dify)
- まず“形”を最速で見せたい?(Yes→Opal)
- ログ/観測性を最初から可視化したい?(LLM中心ならDify)
- 例外処理・再試行・分岐地獄に耐えたい?(n8n)
- 共有しながら会話的に直したい?(Opal)
- 予算は“実行数”で管理したい?(n8nクラウド)
- “メッセージクレジット”で上限を設けたい?(Dify)
- エンジニア・非エンジニアが混在?(n8n+Opalの併用)
- 将来の本番化に耐える設計?(n8n=恒常運用、Dify=LLM運用、Opal=PoC加速)
9|対象読者と“効きどころ”(具体)
- 情シス/ITオペ:アカウント作成・棚卸・ログ連携など定型運用はn8n一本で効率化。外部API障害時の迂回やリトライも設計しやすいです。
- CS/サポート:DifyのRAG+観測性で回答品質の継続改善が可能。文書の誤り訂正→再学習のサイクルをUIで回せます。
- 新規事業/企画:Opalで**“まず見せる”を高速化。Gemini×テンプレで社内デモやユーザヒアリングを促進。良ければn8n/Difyへ昇格**。
- 開発/データ:Difyのモデル横断でコスト・品質AB。n8nで周辺ETLを固める併用が鉄板。
- 経営層/事業責任者:n8nの実行課金とDifyのクレジットで費用予見性を担保。Opalで全社のAIリテラシーを底上げする三段構えが効果的です。
10|“そのまま使える”導入テンプレ(3本)
-
RAGボット要件(Dify向け)
- 目的:社内FAQの一次回答
- データ:最新ハンドブック/ガイド/既知のFAQ
- 指標:正答率/引用率/ハルシネーション率
- 運用:週次でログ確認→アノテーション→再取り込み(UIで完結)
-
SaaS配管(n8n向け)
- トリガー:新規リードの発生
- 処理:重複チェック→名寄せ→スコアリング(AI)→担当アサイン
- 例外:API 429→指数バックオフ、失敗→再実行キュー
-
社内PoC(Opal向け)
- 目標:営業メモ→要点抽出→CRMメモ
- 作り方:自然言語で要件を説明→自動生成されたワークフローを微修正→リンク共有(チームで即試用)
11|よくある質問(Q&A)
Q. Difyは本当に“オープンソースのLLMアプリ基盤”なの?
A. はい。RAG/エージェント/ワークフロー/モデル管理/観測性をUIで統合したオープンソース基盤として案内されています。**対応モデル(OpenAI/Anthropic/Azure OpenAI/Hugging Face/Replicate など)**も公称。
Q. n8nはAI以外の自動化にも強いの?
A. もちろんです。IT/Opsの配管仕事やSaaS連携など、AIに限らない恒常業務の自動化が本領です。AIノードを足してハイブリッドにできます。
Q. Opalは本番運用に向く?
A. プロトタイピング/デモ/社内共有が主眼です。Geminiを活かした**“まず作る”**に強く、**本番運用の枠組み(監査・SLAなど)**は別途設計が必要です。
12|編集部まとめ:結局、どう選べばいい?
- 土台の自動化はn8n。例外・分岐・再試行まで“配管”を作り込み、AIは必要箇所だけを差し込むのが堅実です。
- LLMアプリの本番はDify。RAG/観測性/モデル横断が箱で揃い、**“作る→運用する”**が一直線になります。
- 最速の“まず見せる”はOpal。自然言語→ワークフローでPoCの回数を増やし、良ければn8n/Difyで昇格――この三段構えが2025年の現実解です。
参考(一次・高信頼ソース)
- n8n:製品トップ(AIワークフロー/エージェント)、価格(実行課金・自前ホスト)。
- Dify:製品説明(オープンソースLLMアプリ基盤/RAG・エージェント・観測性)、価格(メッセージクレジット制、上限項目)。
- Opal(Google):開発者ブログ(紹介・用途)、実験版ランディング、第三者解説(無コード・Geminiベース)。
: